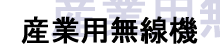
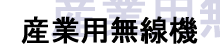
弊社の技術と商品が認められ、宇宙科学研究所(ISAS)所長より感謝状を頂きました。
三陸大気球観測所科学観測大気球プロジェクトにおいて、円滑な商品開発・製作を行い長年にわたりプロジェクトを成功に導いたとして、宇宙科学研究所(ISAS)松尾弘毅所長より、弊社に対して感謝状が贈られました。この感謝状は平成13年5月に開催された三陸大気球観測所開設30周年記念式典において授与され、弊社代表取締役社長の小川が代表して受領してきたもので、
弊社の技術と商品の信頼性が長年にわたり参画しておりました宇宙科学研究所(ISAS)の案件の中で認められた出来事として皆様にお知らせ致します。
平成15年10月に宇宙科学研究所(ISAS)から宇宙航空研究開発機構(JAXA)に統合変更されましたが、山上教授を始め、諸先生方の高度な構想に拠るプロジェクトに現在も継続的にお手伝いをさせて頂いております。
| 宇宙科学研究所(ISAS)とは? |
宇宙科学研究所(ISAS)のルーツは1955(昭和30)年に行われた東京大学のペンシルロケット発射実験にさかのぼります。1964年には東京大学に宇宙科学研究所の前身である宇宙航空研究所が設立され、固体燃料を用いたL-4Sロケットによって日本初の人工衛星「おおすみ」を軌道に送るなど、宇宙理学と宇宙工学が一体となった科学衛星の研究・開発を行ってきました。1981年からは宇宙科学研究所に改組し、全国の大学の共同利用機関としての役割も担ってきました。
宇宙航空事業で日本には3つの組織がありました。宇宙や惑星の研究が中心の「宇宙科学研究所(ISAS)」次世代の航空宇宙技術の研究開発が中心の「航空宇宙技術研究所(NAL)」H-IIAロケットなどの大型ロケットや人工衛星、国際宇宙ステーションの開発が中心の「宇宙開発事業団(NASDA)」の3機関です。
2003年10月1日、ISAS、NAL、NASDAが統合し独立行政法人「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」が誕生しました。
それまで独自のアプローチで未知なる宇宙や空へ挑んできた各機関が3本の矢として束ねられ、基礎研究から開発・利用に至るまで一組織として一貫して行える体制が整ったのです。日本の宇宙航空分野における技術の粋を結集することでその刺激から新たなエネルギーを生み出し、これまで以上に宇宙へのチャレンジを加速する、そんな役割を担っています。新組織JAXAは、国際的にも欧米に肩を並べる機関として、宇宙航空開発の歴史に新たなページを開いています。
| 大気球プロジェクトって? |
科学観測を目的とする大気球の技術は、日本のお家芸の一つです。
金星や木星など、惑星には大気を持つものがあります。こういった天体を探査するときには、着陸機やローバなどに加えて、気球による探査が重要な役割を担うと考えられます。
宇宙科学研究部門では、こういった、大気が存在する惑星で、気球による探査を行えるように、さまざまなな技術開発を行っています。
例えば、火星の大気は地球の100分の1の濃さしかありませんが、金星の大気は地球の100倍近くも濃いものです。温度も、火星のようにマイナス数十度のところもあれば、金星のように、条件によっては非常に高温になる場所もあります。こういった、惑星によってさまざまに異なる大気の違いを克服し、気球による探査ができるような研究が続けられています。
また、地球の大気圏を飛行するための研究も行われています。たとえば、昼夜を問わず、長時間飛行ができるような気球の技術開発も行っています。これらの技術は、NASAの気球にも応用され、大陸を横断して飛行できる気球に活用されています。
※三陸大気球観測所
宇宙科学研究本部は、全国の大学・研究機関と協力して科学観測および宇宙工学実験を行っています。
三陸大気球観測所は、宇宙科学研究本部の施設で科学観測用大気球を飛揚させている日本唯一の恒久施設です。
大気球は数百kgの観測器をジェット旅客機の3倍以上の高度(30〜50km)まで飛揚させることができます。この高度では空気が地上の数百分の一以下になり、空気に妨げられて地上では観測できない宇宙線、紫外線、赤外線、X線、ガンマ線等の観測が可能となります。また、地球環境問題となっているオゾンホール、酸性雨、地球温暖化等についても、大気球を使用することにより直接原因物質を採集測定し、精密に年変化を観測することができます。
大気球は人工衛星やロケットに比べて観測高度では劣るが、ロケットに比べてはるかに長い数十時間の観測を行うことができ、観測機の重量
、容量なども自由に設計できるため先端的な観測器を搭載することが出来ます。また、観測器を回収して再使用も可能なため再現性の良い観測が行えます。大気球は、現在人工衛星、ロケットと並んで宇宙観測用飛翔体として重要な柱の一つとなっています。
昭和46年に三陸大気球観測所が開設以来、約400機以上の大気球がこの観測所から放球されています。
三陸大気球観測所でのひとコマ
| 三陸大気球観測所が三協特殊無線(株)の無線技術を利用している理由は、、、 |
三陸大気球観測所は、飛揚場、指令管制棟、受棟、気球組立棟、大窪山観測棟などから構成されています。気球を放球する飛揚場の広さは、長さ約150m、幅約30mであり、大気球が観測機を載んで成層圏を目指してここから飛んでいきます。飛揚場の一角にある指令管制棟および気球組立棟では放球準備、観測機の調整、放球に必要な指令を行います。
飛翔中の気球からの電波は、受信棟および飛揚場から西南約4kmの山頂にある大窪山観測棟で受信します。また、ここから気球に指令電波を送って観測機を操作したり、気球のコントロールも行います。
市販品では到底まかなえない数々の要望を満たし、悪条件の環境下で高い耐久性を保ち、必要な性能を決められた納期で「開発・製造・供給」出来るサプライヤーは数多くの通信機器企業の中でも数えるほどしかありません。
その中で弊社をお選び頂いているのは、弊社の得意とする小回りの利いた「開発・製造・供給」と出来上がった商品の高い信頼性です。







弊社開発・製造の画像データ送信システムにて送られてきた大気球からの映像
(気球は高度約40Km距離およそ70Kmまで飛翔)